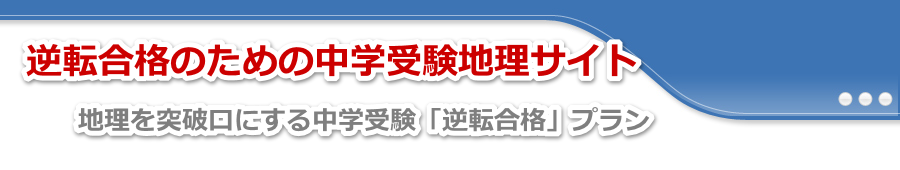
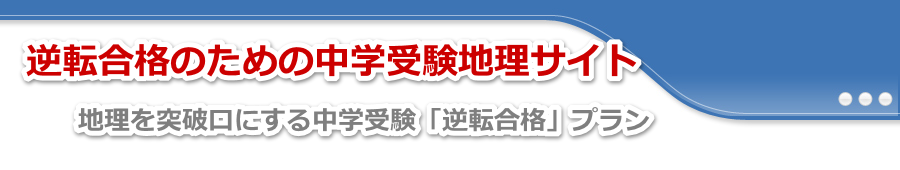
中学受験の地理「四国地方」のポイントまとめ
中学受験社会(地理分野)での四国地方に関する重要ポイントをまとめました。
四国の名前の通り4つの県から出来ているのが四国地方です。

県名だけでなく場所もしっかり覚えるようにしましょう。
- 香川県(東側、瀬戸内海側)
- 徳島県(東側、太平洋側)
- 愛媛県(西側、瀬戸内海側)
- 高地県(西側、太平洋側)
四国で一番面積が広いのは高知県で全国では14位の広さ。
逆に香川県は日本一面積の狭い都道府県です。
四国の地図を見たときに、「一番狭いのが香川県、一番広いのが高知県」と覚えておけば、場所も間違えません。
隣接しているのは徳島県と愛媛県
- 香川県の南側が徳島県
- 愛媛県の南側が高知県
なので、この上下(南北)の組み合わせは県が隣接しています。
四国でひとつだけ接していない県の組み合わせは香川県と高知県です。
徳島県と愛媛県が隣接しているため、香川県と高知県は離れてしまっています。
四国の地図で確認しておきましょう。
右下(徳島県)と左上(愛媛県)が隣接しているというのは、中国地方とは逆のパターンです。
中国地方の4県(山口県除く)では、右上(鳥取県)と左下(広島県)が隣接してます。
瀬戸内海側2県が県名と県庁所在地名が違う
四国地方で県名と県庁所在地名が違うのは瀬戸内海側の2県。
- 香川県…高松市
- 愛媛県…松山市
太平洋側の徳島県と高知県は県名と県庁所在地名が同じです。
四国地方の政令指定都市
四国には政令指定都市が一つもありません。
ただし、高松市、松山市、高知市が中核市(人口30万人以上)に指定されています。
中でも松山市は人口が50万人を超え、四国最大の都市となっています。
四国地方の気候
四国地方の気候は太平洋側と瀬戸内海側で大きく2つに分けられます。
- 太平洋側…沖合を流れる黒潮(日本海流)の影響で年間を通して温暖。
- 瀬戸内海側…年間を通して晴天の日が多く、降水量も少ない
どちらも温暖なことは共通ですが、降水量が違います。
太平洋側は台風の通り道となることも多く、日本でも降水量の多い地域となっています。
逆に瀬戸内海側は年間を通して降水量が少ないのが特徴です。
このため、川が少ない香川県では昔から水不足に悩まされ、
数多くの「ため池」が作られるようになりました。
四国地方の山地
太平洋側と瀬戸内海側を分けているのが四国山地です。
高く険しい山が連なり、南東の季節風を遮っています。
四国で最も高い山は、愛媛県の石鎚山(いしづちさん)。
標高は1,982mで近畿より西では最も高い山です。
近畿より東には高い山が多いのですが、西には2,000mを超える山はありません。
意外なポイントなので要チェックです。
四国地方の平野(讃岐平野と高知平野)
四国地方には各県に1つずつ主に4つの平野があります。
- 讃岐平野…香川県の瀬戸内海沿いに広がる四国最大の平野。
- 高知平野…高知県の中央部に広がる平野。温暖な気候が特徴。
- 徳島平野…徳島県の吉野川下流に広がる平野。
- 松島平野…愛媛県の松山市などを含む平野。
この中でも中学受験でよく出るのは讃岐平野と高知平野です。
讃岐平野は年間を通して降水量が少ないため、ため池が多く作られていることが特徴。
高知平野は温暖な気候を活かした野菜の促成栽培が有名です。
吉野川(別名 四国三郎)
四国最大の川は四国三郎とも呼ばれる吉野川。
高知県から徳島県にかけて流れ、下流域は徳島平野になっています。
四国「三郎」というには、「太郎」と「次郎」もいます。
- 坂東太郎…利根川
- 筑紫次郎…筑後川
この二つに四国三郎(吉野川)を加えて「日本三大暴れ川」とされています。
なお、奈良県にも「吉野川」と呼ばれる川が流れているので間違えないようにしましょう。
高知県には日本最後の清流とも呼ばれる四万十川(しまんとがわ)も流れています。四万十市で2013年8月に日本最高気温の41.0度が観測されたこともあわせて覚えておきましょう。
佐多岬半島
四国の北西(愛媛県)から細長く突き出しているのが佐田岬半島です。
その名の通り先端には佐田岬があります。
室戸岬と足摺岬
佐田岬のほかに四国で覚えておきたいのは2つの岬。
どちら高知県にある室戸岬(むろとみさき)と足摺岬(あしずりみさき)です。
地図で見ると、太平洋に突き出しているところです。
東側にあるのが室戸岬で、西側が足摺岬。
この2つの岬に囲まれたところが土佐湾です。











